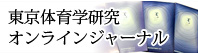3月に開催された東京体育学会の基調講演として、ペンシルバニア州立大学キネシオロジー学部で学部長職にあるPhilip E. Martin教授により、同大学の話をまじえながら、アメリカにおける大学体育の模索と将来戦略についての講演が行われた。
司会の深代千之氏(東京大学)が、「日本においても国立大学が法人化され、種々の大学改革が進行し、ややもすれば大学の体育がスクラップ対象になりかねない状況となり、体育教員が危うい立場に追い込まれやすい。このような状況を回避する方策を考えるためにも、今日の講演は有意義なものになるだろう」と講演の口火をきられたが、そのとおり、私も含め、多くの人が有用な情報を得たいという思いで集まり、真剣に耳を傾けた講演であった。通訳は長野明紀氏(理化学研究所)がつとめられた。
話された主な内容は、「学部の名称の変遷」、「学部の問題や方向性」、「大学院の方向性」、「総括としての将来戦略」であり、その中で強調された点を中心に、記憶をたどりながら、以下にまとめてみる。 学部名称の変遷に関しては次のような話があった。1960年以前の全米では、「physical education」という語が全面に出され体育教員を目指す学部が多かったが、1960~1980年代にかけては、physical educationを用いた学部名が減少し、代わりに「health」という語が多くなり、また「sports,athletes, exercise sciences, movement」 という語も見られるようになったが、その時点では、「kinesiology」という語は殆ど使われず、たった2件(69件中)であったそうである。
ところが2003年になると、physical education の語はほぼ消失し、Kinesiology & Health Education といったように、kinesiology とその造語が学部名に頻繁にみられるようになったそうである。なぜ、学部に、kinesiologyという用語が頻繁に用いられるようになったのかと問われると、「広範で多様性に富んだ内容をもつ体育の現象を包括的に表現できるのが、kinesiologyという用語である」とMartin教授は説明された。広範囲の事象をひとつの視点で捉えられる用語は確かに魅力的であり、それに当てはまるのがkinesiologyという語であるらしい。私達にとっては、深い意味合いやニュアンスが分からないので、またかつて身体運動学をkinesiology(キネシオロジー)と呼んでいたため、古色蒼然の感が払拭できない人も多いのではないかと思われた。
ただ「○○サイエンス」といった英語表現では、たぶん具体的すぎて、用語からイメージされる体育の範囲がかえって狭くなり、それに当てはまらない対象や領域がでできたのではないかと想像される。そのため、包括概念で高尚なラテン語へと回帰していったのかしら...とも考えられた。
名称問題のあと、体育の学部や大学院として活力をもつには、たくさんの課題をうまく制御しなくてはならないことが紹介された。
例えば、実技と理論のカリキュラムのバランスをとること、同じく教育と研究のバランス、また専門領域をどこまで専門化させるのかという範囲の問題、これらに伴う人事配置のバランス、また領域を超えた所で人的協力体制をつくる組織づくりの大切さ(困難さ)、ということが列挙された。人事については、特に体育出身のスタッフとそれ以外のスタッフとの均衡が崩れると、つまり他領域のスタッフが増え過ぎると、human movementやphysical activityという身体運動を基礎にする学問という、「体育」の核心や焦点がぼやけてくること、学生の教育研究が基礎理論に偏向しすぎること、また体育をめざす学生のニーズから遊離しやすいこと、といった危険性やデメリットが指摘された。
体育出身者が継続してスタッフとなりやすい社会学、歴史学、心理学などの領域に比べ、運動生理学、バイオメカ二クス、運動制御学等の自然科学領域では、他領域からの参入者が多くなりがちだというアメリカの現状も話された。これらの領域では、高い学術成果に対する評価が重視されるため、そしてそれらはポスドク経験の豊かさとグラント獲得率の高さに比例するものなので、体育出身者よりも他領域出身のスタッフが当然ポストを占有しやすくなるのだ、という説明があった。
その話を聞きながら、明確なコメントはなかったが、高い学術成果の重要性を認識することは大切であるが、それに偏重し過ぎると、上述した問題や不利益が学部内に生じ、最終的には本質を見失う....という注意を受けたような気がした。バランス良い人事をすることは確かに難しい課題である。
また学部教育について、次のような話もされた。ペンシルベニア州立大学の場合、約15%の学生は実技やトレー二ングという実践に興味を持つが、70%以上の多数の学生が、movement sciencesといった科学的基礎や理論部分に興味を持っているということである。さらに希望職種が、教師、トレーナー、研究職、スポーツコマーシャル業界、マスコミ関係などと多岐にわたるという調査を踏まえ、これらを括る共通項目が何であるのかを議論し、その上で「exercise activity」や「human movement」が全ての共通項目であるという認識を得たので、その共通項目に履修の重点をおくようにカリキュラムを変更したということである。
具体的には、historyとphilosophy,psychologyとsociologyをペアとして、そのペアからどちらかを選択するようにして履修範囲を限定し、同時に、exercise physiologyという科目は2つに増やすことに決め、そして単に増やすだけではなく、専門家としてのキャリア育成を目標としたexercise physiologyと体育教師やトレーナーに必要な知識獲得を目標としたexercise physiologyという、内容に変化をもたせるようにしたというのである。
このように学生の多様な要望に応え、学生を満足させられるように工夫することの大切さが語られた。 さらに大学院教育においては、基礎研究に重点がおかれた従来の大学院のあり方ではなく、専門の「教育」にもっと真剣に取り組み、基礎研究だけでなく、学際領域や開発に関わる研究にも力点をおくことが大切、と教授は強調された。特に学生の就職先を考慮すると、広領域に通用する人材を育成する必要があり、このため、特定の専門に特化した学術的知識レベルを評価するだけではなく、
(1) 大学院生が2つ以上の研究室で研鑽を積み、多様な専門に通じるキャリアを有しているのかどうか
(2) コミュニケーションやディスカッション能力を獲得し、リーダーシップ能力が高いのかどうか
(3) 研究やプロジェクトの企画立案や経費申請等の企画推進力を有するのか
といった学術以外の基準も修了要件に盛り込むようにすると話されていた。 このような具体案は、日本における大学院教育を活性化させるために利用できる方策だと思われ、興味深く聞きいった。
そして最後に、全体をまとめる意図で、発展的な大学に必要な戦略プランとして次のような点が指摘された。
(1) 明確な理念とプログラムを明示すること
(2) カリキュラムがしっかりとした教育をめざし、高い市場価値を有する学位にすること
(3) 非常に高い学術成果を持つこと
(4) 優れた教育に力をいれること
(5) 実技現場に近い理論に力をいれること
(6) 教育と研究の両面のバランスが保たれること
といった6ポイントであった。 さらに管理運営の立場から
(1) 教員・スタッフ全員が共通目標に向い、それぞれが固有の能力を発揮できる組織をつくり、全員が一体感を持てるようにすること
(2) 体育学部が大学全体の組織にとって有益で掛け替えのない存在になるようにすること
(3) 適応力のある柔軟な学部づくりに努めること,といったことも指摘された
このようなMartin教授の話の中で、「もっと深く議論したい、具体策のヒントが欲しい。」と感じた人も多かったと思われる。しかし、それは私達一人一人が独自に考えるしかない、使命なのだと思われる。こうすればうまく行くだろうという成功モデルもなく、過去の経験から推し測ることもできない大学変革に途方にくれているが、自分たちで叡智を絞りだし、大学体育の存亡をかけた活路を見出すべきなのだろう。そんなことを感じながら、講演を聞き終えた。
司会の深代千之氏(東京大学)が、「日本においても国立大学が法人化され、種々の大学改革が進行し、ややもすれば大学の体育がスクラップ対象になりかねない状況となり、体育教員が危うい立場に追い込まれやすい。このような状況を回避する方策を考えるためにも、今日の講演は有意義なものになるだろう」と講演の口火をきられたが、そのとおり、私も含め、多くの人が有用な情報を得たいという思いで集まり、真剣に耳を傾けた講演であった。通訳は長野明紀氏(理化学研究所)がつとめられた。
話された主な内容は、「学部の名称の変遷」、「学部の問題や方向性」、「大学院の方向性」、「総括としての将来戦略」であり、その中で強調された点を中心に、記憶をたどりながら、以下にまとめてみる。 学部名称の変遷に関しては次のような話があった。1960年以前の全米では、「physical education」という語が全面に出され体育教員を目指す学部が多かったが、1960~1980年代にかけては、physical educationを用いた学部名が減少し、代わりに「health」という語が多くなり、また「sports,athletes, exercise sciences, movement」 という語も見られるようになったが、その時点では、「kinesiology」という語は殆ど使われず、たった2件(69件中)であったそうである。
ところが2003年になると、physical education の語はほぼ消失し、Kinesiology & Health Education といったように、kinesiology とその造語が学部名に頻繁にみられるようになったそうである。なぜ、学部に、kinesiologyという用語が頻繁に用いられるようになったのかと問われると、「広範で多様性に富んだ内容をもつ体育の現象を包括的に表現できるのが、kinesiologyという用語である」とMartin教授は説明された。広範囲の事象をひとつの視点で捉えられる用語は確かに魅力的であり、それに当てはまるのがkinesiologyという語であるらしい。私達にとっては、深い意味合いやニュアンスが分からないので、またかつて身体運動学をkinesiology(キネシオロジー)と呼んでいたため、古色蒼然の感が払拭できない人も多いのではないかと思われた。
ただ「○○サイエンス」といった英語表現では、たぶん具体的すぎて、用語からイメージされる体育の範囲がかえって狭くなり、それに当てはまらない対象や領域がでできたのではないかと想像される。そのため、包括概念で高尚なラテン語へと回帰していったのかしら...とも考えられた。
名称問題のあと、体育の学部や大学院として活力をもつには、たくさんの課題をうまく制御しなくてはならないことが紹介された。
例えば、実技と理論のカリキュラムのバランスをとること、同じく教育と研究のバランス、また専門領域をどこまで専門化させるのかという範囲の問題、これらに伴う人事配置のバランス、また領域を超えた所で人的協力体制をつくる組織づくりの大切さ(困難さ)、ということが列挙された。人事については、特に体育出身のスタッフとそれ以外のスタッフとの均衡が崩れると、つまり他領域のスタッフが増え過ぎると、human movementやphysical activityという身体運動を基礎にする学問という、「体育」の核心や焦点がぼやけてくること、学生の教育研究が基礎理論に偏向しすぎること、また体育をめざす学生のニーズから遊離しやすいこと、といった危険性やデメリットが指摘された。
体育出身者が継続してスタッフとなりやすい社会学、歴史学、心理学などの領域に比べ、運動生理学、バイオメカ二クス、運動制御学等の自然科学領域では、他領域からの参入者が多くなりがちだというアメリカの現状も話された。これらの領域では、高い学術成果に対する評価が重視されるため、そしてそれらはポスドク経験の豊かさとグラント獲得率の高さに比例するものなので、体育出身者よりも他領域出身のスタッフが当然ポストを占有しやすくなるのだ、という説明があった。
その話を聞きながら、明確なコメントはなかったが、高い学術成果の重要性を認識することは大切であるが、それに偏重し過ぎると、上述した問題や不利益が学部内に生じ、最終的には本質を見失う....という注意を受けたような気がした。バランス良い人事をすることは確かに難しい課題である。
また学部教育について、次のような話もされた。ペンシルベニア州立大学の場合、約15%の学生は実技やトレー二ングという実践に興味を持つが、70%以上の多数の学生が、movement sciencesといった科学的基礎や理論部分に興味を持っているということである。さらに希望職種が、教師、トレーナー、研究職、スポーツコマーシャル業界、マスコミ関係などと多岐にわたるという調査を踏まえ、これらを括る共通項目が何であるのかを議論し、その上で「exercise activity」や「human movement」が全ての共通項目であるという認識を得たので、その共通項目に履修の重点をおくようにカリキュラムを変更したということである。
具体的には、historyとphilosophy,psychologyとsociologyをペアとして、そのペアからどちらかを選択するようにして履修範囲を限定し、同時に、exercise physiologyという科目は2つに増やすことに決め、そして単に増やすだけではなく、専門家としてのキャリア育成を目標としたexercise physiologyと体育教師やトレーナーに必要な知識獲得を目標としたexercise physiologyという、内容に変化をもたせるようにしたというのである。
このように学生の多様な要望に応え、学生を満足させられるように工夫することの大切さが語られた。 さらに大学院教育においては、基礎研究に重点がおかれた従来の大学院のあり方ではなく、専門の「教育」にもっと真剣に取り組み、基礎研究だけでなく、学際領域や開発に関わる研究にも力点をおくことが大切、と教授は強調された。特に学生の就職先を考慮すると、広領域に通用する人材を育成する必要があり、このため、特定の専門に特化した学術的知識レベルを評価するだけではなく、
(1) 大学院生が2つ以上の研究室で研鑽を積み、多様な専門に通じるキャリアを有しているのかどうか
(2) コミュニケーションやディスカッション能力を獲得し、リーダーシップ能力が高いのかどうか
(3) 研究やプロジェクトの企画立案や経費申請等の企画推進力を有するのか
といった学術以外の基準も修了要件に盛り込むようにすると話されていた。 このような具体案は、日本における大学院教育を活性化させるために利用できる方策だと思われ、興味深く聞きいった。
そして最後に、全体をまとめる意図で、発展的な大学に必要な戦略プランとして次のような点が指摘された。
(1) 明確な理念とプログラムを明示すること
(2) カリキュラムがしっかりとした教育をめざし、高い市場価値を有する学位にすること
(3) 非常に高い学術成果を持つこと
(4) 優れた教育に力をいれること
(5) 実技現場に近い理論に力をいれること
(6) 教育と研究の両面のバランスが保たれること
といった6ポイントであった。 さらに管理運営の立場から
(1) 教員・スタッフ全員が共通目標に向い、それぞれが固有の能力を発揮できる組織をつくり、全員が一体感を持てるようにすること
(2) 体育学部が大学全体の組織にとって有益で掛け替えのない存在になるようにすること
(3) 適応力のある柔軟な学部づくりに努めること,といったことも指摘された
このようなMartin教授の話の中で、「もっと深く議論したい、具体策のヒントが欲しい。」と感じた人も多かったと思われる。しかし、それは私達一人一人が独自に考えるしかない、使命なのだと思われる。こうすればうまく行くだろうという成功モデルもなく、過去の経験から推し測ることもできない大学変革に途方にくれているが、自分たちで叡智を絞りだし、大学体育の存亡をかけた活路を見出すべきなのだろう。そんなことを感じながら、講演を聞き終えた。